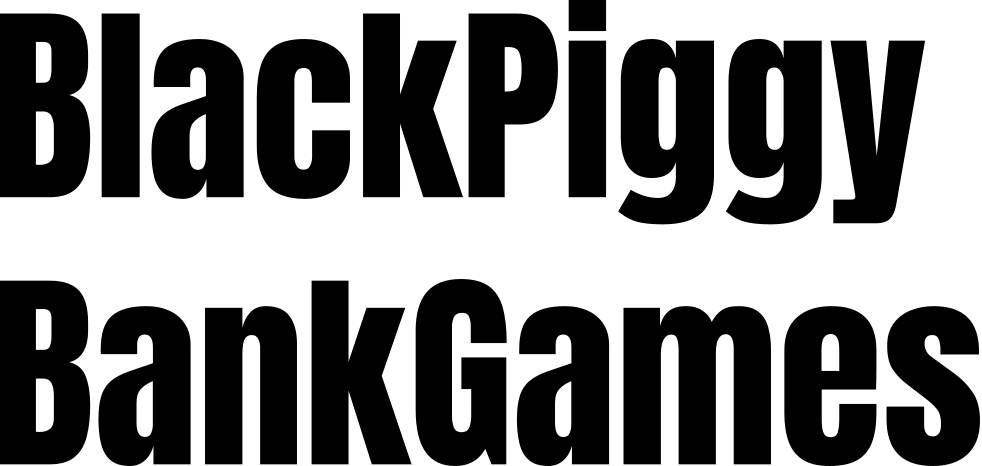アイデンティティ崩し
2025-05-11 17:20 · 3422 words · 7 minute read
コンセプト
ゲームのアイデンティティを探り、共有するメタゲーム。プレイヤーそれぞれが持つ「このゲームをこのゲームたらしめている要素」を出し合い、話し合いを通じてより深い理解を得ることを目指します。
アイデンティティについて
このゲームでは、「アイデンティティ」とは「このゲームをこのゲームたらしめている要素」を指します。例えば、将棋というゲームであれば、「駒を交互に動かす」「相手の王将を詰める」といった要素が、そのゲームのアイデンティティとなります。
メタゲームについて
メタゲームとは、既存のゲームの上に新しい遊びのレイヤーを追加するゲームのことです。このゲームでは、プレイしたことのあるゲームについて、「そのゲームのアイデンティティを探り、共有する」という新しい視点で遊びます。例えば、将棋をプレイした経験を元に「将棋のアイデンティティは何だろう?」と考えるような、ゲームについてのゲームです。
ゲームの概要
このゲームは、特定のゲームのアイデンティティを探り、共有するためのメタゲームです。プレイヤーは各自が考える「そのゲームのアイデンティティ」をカードに書き、それを出し合います。その後、より重要でないと思うカードを取り除いていきます。この過程で、プレイヤーの過半数が「そのゲームのアイデンティティが失われてしまった」と判断した時点でゲームオーバーとなります。
ジャンル
メタゲーム / 対話ゲーム / 教育ゲーム
このゲームは以下の特徴を持ちます:
- メタゲーム:既存のゲームのアイデンティティを探り、共有する
- 対話ゲーム:プレイヤー間の話し合いを通じて、より深い理解を得る
- 教育ゲーム:ゲームのアイデンティティについての理解を深める
ゲームの基本的な流れ
- 対象となるゲームを選ぶ
- 各自が考える「ゲームのアイデンティティ」をカードに書く
- カードを出し合い、より重要でないと思うカードを取り除く
- プレイヤーの過半数が「そのゲームのアイデンティティが失われてしまった」と判断した時点でゲームオーバー
目的
対象となるゲームのアイデンティティを探り、共有することを通じて、より深い理解を得ることを目指します。
プレイヤー人数
3-6人推奨
用意するもの
対象となるゲーム
- 参加者全員がプレイしたことがあるゲームを選ぶ
- ボードゲーム、カードゲーム、ビデオゲームなど、ジャンルは問わない
紙
- 参加者1人につき3枚の紙を用意する
- 名刺サイズ(約91mm × 55mm)程度の大きさが適している
- この紙にゲームのアイデンティティを書いたものが「アイデンティティカード」となる
- アイデンティティカードは、ゲーム中にテーブルに並べて共有する
- アイデンティティカードは、ゲームの進行に応じて取り除かれていく
ブレインストーミング用の共有ツール(任意)
- 大きな紙(A1サイズ程度)またはホワイトボード
- 付箋(複数色があると分類しやすい)
- マーカー(複数色)
※ 共有ツールがあると、全員のアイデアを視覚的に共有でき、より効果的なブレインストーミングが可能になります。付箋を使うことで、アイデアの分類や整理も容易になります。ただし、必須ではありません。
ペン
- 参加者人数分
準備
- 対象となるゲームを選ぶ
- 参加者全員に、紙とペンを配る
- このゲームの目的を全員で共有する
ルール
1. アイデンティティカードの作成
- まず、全員で対象ゲームの重要な要素を簡単にアイデア出しをする
- 制限時間を設け(例:5-10分)、思いつく要素を自由に挙げていく
- 具体的な要素でも抽象的な要素でも構わない
- 他の人の意見を聞いて、新しい要素を思いついたら追加していく
- 共有ツールがある場合は、付箋に要素を書き、大きな紙やホワイトボードに貼り付けていく
- 共有ツールがある場合は、似た要素は近くに配置し、関連性を視覚的に表現する
- 共有ツールがある場合は、必要に応じて、要素を分類したり、関連性を線で結んだりする
- アイデア出しで出た要素の中から、各自が重要だと思う要素を選んでアイデンティティカードを作成する
- 自分が「このゲームをこのゲームたらしめている」と考える要素を、重要度の高い順に3つ選ぶ
- この選択は秘密に行い、他のプレイヤーの影響を受けないようにする
- 選んだ要素を紙に書き、その理由も簡単にメモしておく(これがアイデンティティカードとなる)
- 全員が選び終わったら、順番に選んだ要素とその理由を説明する
- 同じ要素を複数のプレイヤーが選んでも構わない
- むしろ、複数のプレイヤーが同じ要素を選ぶことは、その要素が重要だという証拠となる
- カードの総数は、参加人数×3枚程度を目安とする
2. カードの確認
- 全員のアイデンティティカードをテーブルに並べ、内容を確認する
- 不明な点があれば、その時点で質問や意見を述べることができる
3. スタートプレイヤーの決定
- 適当な方法(例:サイコロを振る、じゃんけんなど)でスタートプレイヤーを決める
- スタートプレイヤーから時計回りに順番が回っていく
4. カードの除去
- スタートプレイヤーから順番に、より重要でないと思うカードを1枚ずつ取り除いていく
- 取り除く際は、できれば簡単に理由を述べる
- 全員が1回ずつカードを除去したら、次のラウンドに移る
- 各ラウンドで1人1枚ずつカードを除去していく
5. ゲームオーバー
- カードが除去されるたびに、以下の手順で判定を行う:
- カードを除去したプレイヤー以外は、そのカードに書かれた要素がそのゲームのアイデンティティとして重要かどうかを考える
- まだ「ゲームのアイデンティティが失われた」と判断していないプレイヤーは、考えがまとまったら手をあげて待つ
- 全員が手をあげたら合図で、一斉に手を下す
- そのカードがなくなったらそのゲームのアイデンティティが失われると思ったプレイヤーは、手をおろした後、親指を立ててそれ以外の指を握る(「ゲームのアイデンティティが失われた」を示すポーズ)
- そのカードがなくなってもそのゲームのアイデンティティは保たれると思ったプレイヤーは、手をおろした後、そのまま待つ
- 一度「ゲームのアイデンティティが失われた」と判断したプレイヤーは、以降の判定でも同じポーズを維持する
- 「ゲームのアイデンティティが失われた」と判断したプレイヤーの人数が過半数を超えていたらゲームオーバー
- ゲームオーバーとなった時点で、残っているカードの内容を確認する
- 全員で、なぜそのカードが残ったのか、なぜそのカードが重要だと思うのかを議論する
ヒント
- カードを書くときは、ゲームの具体的な要素に焦点を当てましょう:
- ゲームのルール(例:「駒を交互に動かす」「カードを引く」)
- プレイヤーの行動(例:「サイコロを振る」「相手の駒を取る」)
- ゲームの進行方法(例:「順番に手番が回る」「特定の条件で勝利」)
- カードを除去する際は、簡単でいいので必ず理由を述べ、話し合いを促す
- ゲームオーバーとなった時点で、残っているカードの内容を確認し、全員で議論する
FAQ
カードの内容は具体的にどのようなものですか?
カードには、ゲームの具体的な要素を書きましょう。例えば:
- ゲームのルール:
- 「駒を交互に動かす」(将棋の場合)
- 「カードを引く」(トランプの場合)
- 「サイコロを振る」(すごろくの場合)
- プレイヤーの行動:
- 「相手の駒を取る」(将棋の場合)
- 「カードを捨てる」(トランプの場合)
- 「マスを進む」(すごろくの場合)
- ゲームの進行方法:
- 「順番に手番が回る」
- 「特定の条件で勝利する」
- 「特定の条件で敗北する」
※ 抽象的な要素(例:「戦略性」「運の要素」など)は、具体的な要素の組み合わせとして説明できることが多いため、このゲームでは具体的な要素に焦点を当てます。
カードを除去する際の基準は何ですか?
より重要でないと思うカードを取り除きます。例えば:
- その要素がなくなっても、ゲームの基本的な楽しさは変わらないと思う場合
- その要素は他の要素の一部として含まれている場合
- その要素は必須ではないと考える場合
ただし、簡単でいいので必ず理由を述べ、話し合いを促してください。他のプレイヤーの意見を聞くことで、新しい発見があるかもしれません。
ゲームオーバーとなった時点で、残っているカードの内容を確認するのはなぜですか?
残っているカードの内容を確認し、全員で議論することで、より深い理解を得ることができます。例えば:
- なぜその要素が重要だと考えられたのか
- その要素がゲームにどのような影響を与えているのか
- 他のプレイヤーはその要素をどのように捉えているのか
デザインノート
気が向いたら!